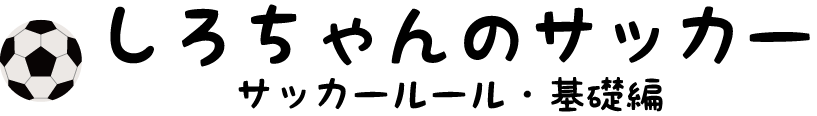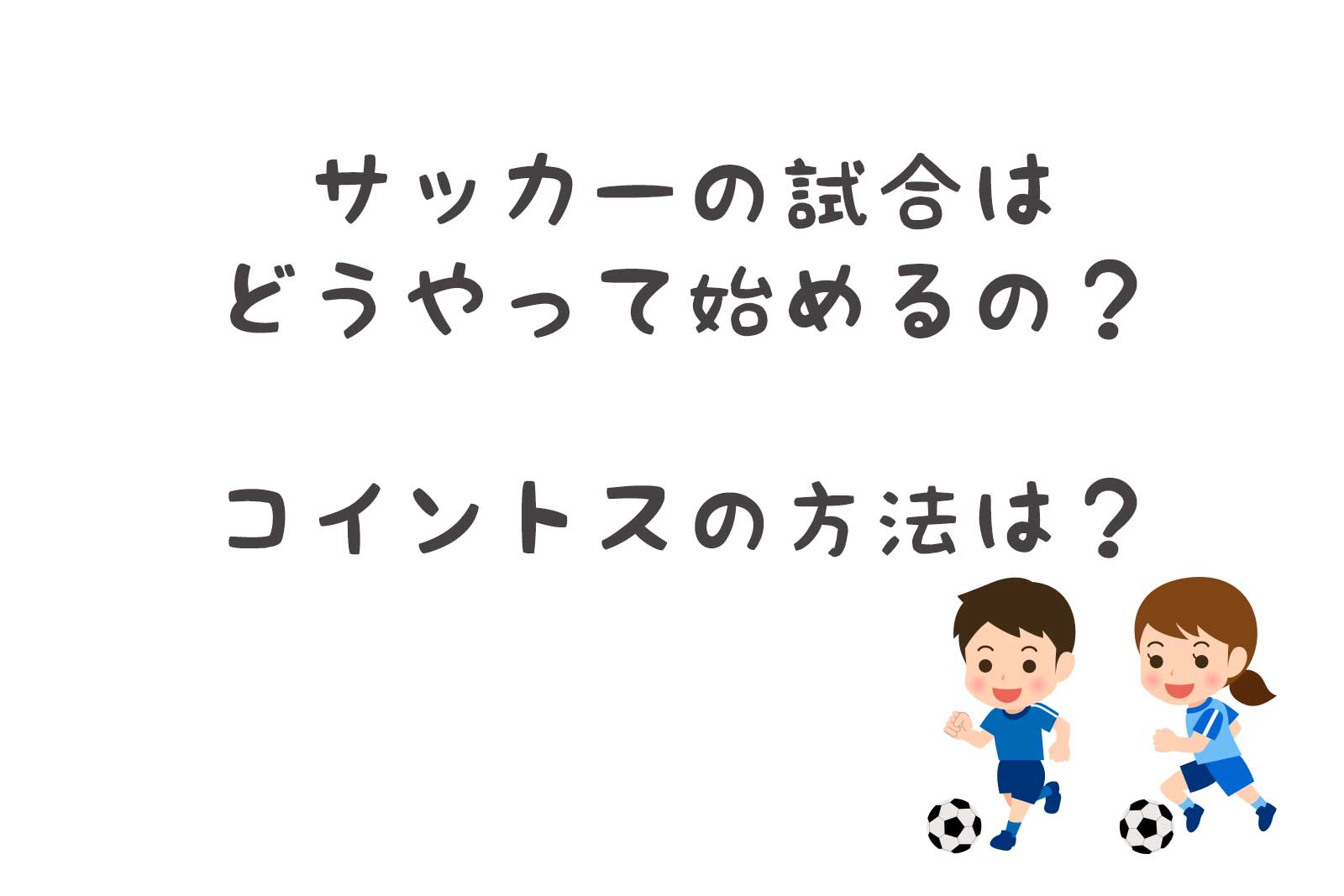サッカーの試合は必ずどちらかのチームのボールからキックオフされます。
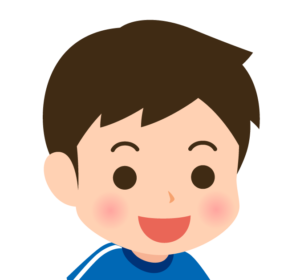
試合前に審判とキャプテンが何やら話し合っているところは見たことがあればそこで決めていることは想像できますが、実際にどのようなルールで決めているのでしょうか。
キックオフの仕方も戦術上とても大事になってきますのでそのやり方、決め方についてご説明していきます。
キックオフのやり方

キックオフとはボール保有権があるチームがボールを蹴りだして試合を始めることを指します。
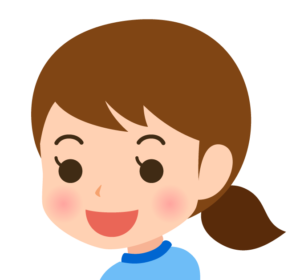
蹴る方向はどこでも良いですが、蹴った人は次に誰かが触るまではボールに触れられないのでドリブルは禁止です。
ちなみに2016年に一部キックオフのルールが変わっていますので、以前はキックオフでは前に絶対に蹴らなければならなかったので味方が側にいて、ほんの少し前に蹴ったボールを受けてスタートするのが常識でした。
そのため2人でキックオフのために準備をするのが一般的でしたが、現在のルールになってからはキックオフの時にボールの近くにいるのは1人だけということは珍しくありません。
キックオフはフリーキックと同じような扱いですので誰にも邪魔をされずに蹴ることができ、直接ゴールを狙うことも可能です。
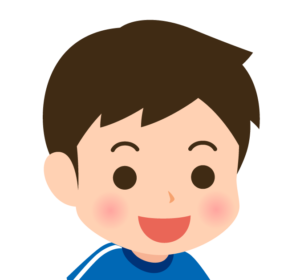
キックオフでボールを動かしてからフォーメーションプレーを仕掛けてくるチームも時々みかけますが、キックオフのボールをどう扱うかによって、いきなりビッグチャンスを生み出すことも不可能ではないので、ただの試合のスタートの合図と考えて疎かにはできません。
試合前のコイントスで決めていること

キックオフでどちらのチームがボールを持って始めるかは試合前にコイントスを行って決めます。
以前はコイントスで勝ったチームがどちらの方向に向けて攻めるか決めていて、必然的に負けた方のボールからキックオフすることになっていました。
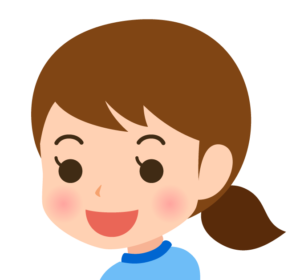
2019年のルール改定からはコイントスに勝った方が攻める方を決めてもボールを持つかどうかを決めてもよくなりました。
キックオフからチャンスを作ることも可能ですので先制攻撃を仕掛けたいならボールを選ぶこともでき、自由度が増したことになります。
コイントスとはコインを投げて裏表で判断するものです。主審はトスコインを持っているのでそれを使って行います。
コイントスのやり方には決まりがない
キックオフを決める大切なコイントスですが、実はそのルールは審判が行うということ以外はそこまで厳密に決まっていません
投げるコインすら決まっていないので審判の好みで記念のコインなどを使っている人もいるくようです。
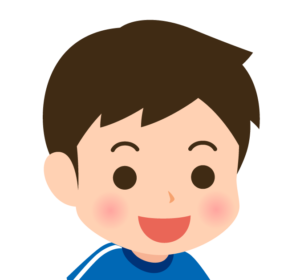
投げかたも決められているわけではないので公平に上に投げられていれば何でも大丈夫です。
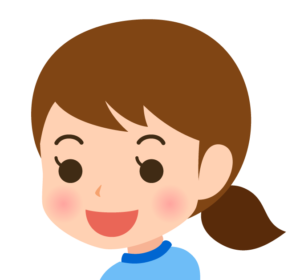
AチームとBチームのどちらがコインの表を選んでいるかも気になるところですが、やり方は審判ごとに違います。
両チームのキャプテンに「どちらにする?」と聞く人もいれば「Aチームは表ね」と決めてしまう人もいます。
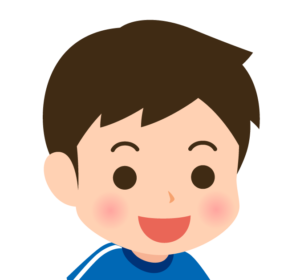
エンドの重要性は天気次第

最初のコイントスで、最初に蹴ることができるチーム、攻める方向を決めるチームのそれぞれを決めます。
攻める方向、サッカーでは陣地を指すエンドと呼ぶのが一般的ですがエンド選びで試合展開が変りかねません。
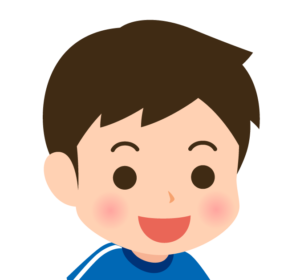
逆風の中で攻めるのは大変ですので風下に向かって攻める方向を選んだ方が有利になるのは明白で、後半になると風向きは変わるかもしれないので先に有利に試合を進めるためにエンドを選ぶことになります。
日差しが強い日も太陽を背にしていた方が守りやすく、特にゴールキーパーにとっては太陽の向きはとっても大切!
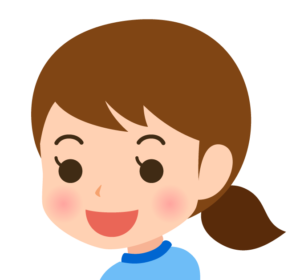
プロチームのエンド選びは暗黙の了解がある?
プロの試合ですとエンドは前半は自分のチームのサポーターを背にして攻撃をして、後半はサポーターの方向に向かって攻めるという場合がほとんどです。
試合終了間際に劇的なゴールが決まってサポーター席に走って行って喜びを表すシーンを見たことがあるかもしれませんが、そんな名シーンもエンド決めによって生まれているということです。
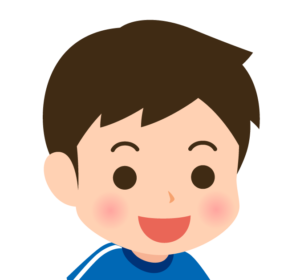
まとめ
キックオフは試合のスタートであると同時に最初のチャンスでもありますので大事にしたいとことです。
ですが天候によってはエンドを選んだ方が良い場合もありますので、そこは作戦次第ですね!